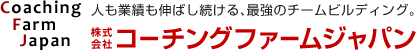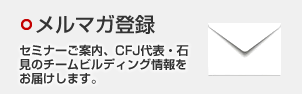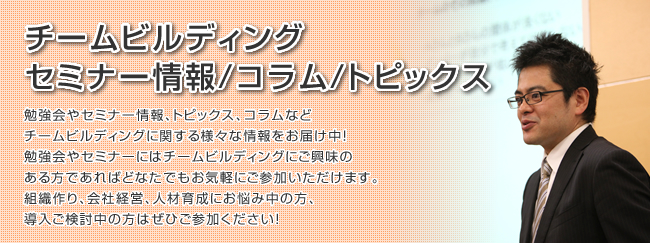
チームビルディングが付加価値を創造する
「リーダーにとって本物の決断力はどこから醸成されるのか」
どんなチームにおいても必要不可欠な存在がチームリーダー。
仕事の現場では主に管理職と言われる人がリーダーと目されるのだが、
リーダーとリーダーシップに関しては言われるまでもなく違うものです。
一般的にはリーダーとは与えられるものであり、リーダーシップは生まれ出てくるもの、もしくは湧き上がってくるものといわれます。厳密にいえばもちろん、リーダーとは与えられる「肩書き」です。本当のリーダーとは選ばれる人であり、周りに支持され認められるものであるのは間違いはありません。
そのような視点でいえば、決断力とは私たちが「リーダーシップ」を語る時に、必ずといっていいほど取り上げられる言葉であり要素でもあります。それではリーダーにとって決断力を付けるためにやることは何か。シンプルに言えば「常に新しい事にチャレンジして成果を残す事」。この1点につきます。
これをやれば、必ず決断力は身に付きます。それも本物の決断力が付きます。カリスマと言われるリーダーはそれをやり続けている人であり、新しい事やハードルがとてつもなく高い事にチャレンジし続けている人でもあります。
リーダーシップの開発とは【新しい分野で成果を残す】ことに全てが凝縮されています。新しい領域では、未知だからこそ生まれる恐怖感とその領域をうまく切り開くことが出来るかどうかの不安感が常に湧き上がってきます。そして、今までの考え方ややり方という経験則が通用するかどうかわからない中で進まざるを得ないのです。
この未知な領域で、湧き上がる恐怖感と不安感と戦いながら【決める】作業を実践することで本物の決断力が身に付くのです。そして、その未知な領域であっても成果を残す事ができる、若しくは残すために全身全霊をかけて物事にあたることこそが人を大きく成長させるのです。例えていえば、ジャングルの中で一歩一歩「こっちに進んでいいのか、ここに足を置いていいのか」と常に問いかけながら進み、最後には必ず目的地へ辿り着く、そんな事ではないでしょうか。そのような視点からいえば、たとえ仕事上で管理職やリーダーと言われる人であっても、新しい領域の仕事をしていない人には本物の決断力は身につきません。既知の領域で決める事はそれほど難しくなく、ストレスもかからないからです。既知の領域ばかりで仕事をしている人は大きな成長は望めません。経験により判断力は磨かれますが、【決断力】は身に付かないのです。
そして【常に】という事が大事になってきます。人間一度や二度であれば新しい事をチャレンジをすることはできます。ですが、それを常にやるとなるとハードルが高くなります。どうしても人間は、既知の世界でやっていたいという防御反応が生まれるからです。それを一般的には「楽な方向、楽な方向でやってしまいたくなる」という表現を使います。一番大事な事は、
「あなたのいる組織は、新しい領域で常に仕事をするよう求められているか」
「あなたのいる組織は、目の前のうまくいかない事を認める組織風土かどうか」
これが、リーダーが【決断力】を付けるために大事になってきます。よくあるのは、数字としての成果は高い=新しい領域でのチャレンジがうまくいかない時に、すぐにうまくいかないことに反応してしまい、「それはうまくいかないんじゃないか」や「こうやれ、そうやれ」と言い放ったりしてしまうことです。大局的に観ると、そのような組織ではリーダーとして【決断力】を身につけることができないですし、やがてリーダーが排出されない組織になります。その行きつく先は、ダイナミズムを失った右肩下がりの結果しかでない組織であり、やがて組織はなくなっていくしかないという現実です。
その未知への領域に足を踏み入れ、成功を収めるためには、チームビルドされたチームで事にあたることです。それはうまくいかない事を極力減らし、うまくいくチャンスを未知な領域でも増やし、成功する確率を上げる事になるからです。そしてリーダーは協力的なメンバーが1人でも多いとリスクに感じる【決断】を決めやすくなります。そのチームビルドされたチームからは、リーダーは次から次へと排出されます。あなたの組織は、そしてあなたのリーダーは